今回は本当にいろいろな「雑魚(ざつぎょと読んでね)」が手に入ったので、色々な料理を試すことができた。
カゴカキダイの刺身が本当に脂がのっているということや、
アカヤガラを干物にして焼くと皮目がパリッとして美味しいこと、
本当に新鮮なスルメイカの肝はわさび塩で食べると絶品だということ(アニサキス怖いけど)
など、新たな発見があってとても楽しかった。
網代の定置網はパラダイスだ。
これからも末永く楽しませてもらいたいと思っている。
ナンプラーで「くさやモドキ」をつくる
さて、魚たちのうち刺身にならなかったものは、みりん干しや酒干しなどの干物にして保存することにしたのだが、一つ試してみたいものがあった。
それはずばりくさやである。
といっても、本気でくさやを作ろうと思ってもくさや液が手に入らない。
ネットを見ると数多の人間がくさや液づくりに挑戦し、そして轟沈している。
ただでさえ難しい発酵食品であるうえ、伊豆七島の気候や伝統など、素人では再現できないところが多いのだろう。
また、仮にくさや液が手に入っても、集合住宅に住む現在ではくさや作りも調理もできない。
何度か購入しようと思い立ったが、焼くときの匂いを考えるとどうも踏み出せないのだ。(なので伊豆大島でしか食べたことが無い)
というわけで、今回作るものは「自家製くさやモドキ」である。
wikipediaによると
-くさや液は、茶褐色の粘り気のある液体で魚醤に近い風味をもつ。-(wikipedia「くさや」より引用)
ということで、なんらかの魚醤で干物を作ればそれっぽいものになるのではないか、と思ったのだ。
現在自宅にある魚醤は
・ナンプラー
・ニョクマム
・いしる
だが、嗅ぎ比べた結果もっとも匂いの強かった
ナンプラーで作ることにした。
自家製くさやモドキを食べる
作り方はこれまた簡単で、下処理をして立て塩にした魚をナンプラーにドボンと漬け、一晩漬けてから汁気を切り、風通しの良い野外で好きなだけ干す。
途中悪天候に当たってしまい、台所で干すことになったが、換気扇を全力で回すことになってしまいとても寒い思いをした。
それでも、艶めかしげなべっこう色に光る、くさやモドキが無事完成した。
伊豆諸島ではどんな魚もくさやの材料にしてしまうということだが、それでもミノカサゴやアカヤガラのくさやなんてあまりないのではないか。
カゴカキダイ、メイタガレイでも挑戦してみた。
このような変わった魚のくさや(モドキ)を食べられるのが自家製のいいところだ。
この時点で匂いを嗅いでみると、あまり臭くない。
ナンプラーそのものの匂いと比べても、かなり穏やかで、非常においしそうな匂いがする(くさやの匂いをdisっている訳ではありません)
ただ本家くさやも、焼く前の臭気は納豆と同程度らしいが、焼くとかなりのものになるのでまだ油断はできない。
フライパンに魚焼き用ホイルをしいて、おそるおそる焼いてみると…
少しだけ匂いがするが、くさやのそれとは全然レベルが違う。
確かに普通の干物と比べると多少くせがあるが、よそ様の迷惑になるようなものではない。
焼き上がり。
早速食べてみると、
(>~<)…
…
味、濃いわぁ…
まず、塩分が濃い。鮭でいうと辛口くらいで、ソウダガツオのように切り身で漬けたものだとややしょっぱすぎる。
くさや液の塩分濃度が13%程度なのに比べ、ナンプラーは20%以上あるので、そこを考慮するべきだったようだ。
ただ同時に、うまみも非常に強い。
本家くさやにはかなわないものの、通常の干物と比べると段違いのうまみである。
これ、焼いてほぐしてお茶漬けにしたら何杯でもいけるわぁ…
単体でも、山廃純米酒などあれば止まらないだろう。
味:★★★★☆
価格:★★★☆☆ 魚醤をふんだんに使うのでちょっと贅沢な干物だ。
味も匂いも本家と比べると弱いが、マンションでも焼けるくさやという考え方をすればなかなか価値のあるものだと思う。
ただナンプラーだとやや塩分が強すぎるので、漬け時間を短くするか、より塩分濃度の低い魚醤を見つけられたらそれが一番だろう。
いしるでも試してみようかな。
魚醤から自作するという手もあるが…まあ、これは今後の課題。
-logo1-3.png)



















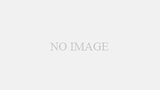
コメント